相続した不要な”負”動産を手放せる?相続土地国庫帰属制度について
みなさんこんにちは。須賀川市で相続を専門に取り扱っています司法書士の黒田匠です。
近年、都市部への人口集中や高齢化が進む日本において、利用予定のない土地を相続される方が増えています。遠方に住んでいて管理が難しかったり、固定資産税の負担が重かったりと、相続した土地が予期せぬ悩みとなることも少なくありません。
このような背景から、令和5年4月27日に「相続土地国庫帰属制度」という新たな法律が施行されました 。
この制度は、相続または相続人に対する遺贈によって取得した土地で、今後利用する予定のない場合に、一定の条件を満たせばその土地の所有権を国庫に移転できるというものです 。
この制度の創設は、所有者が不明な土地の増加を防ぎ、既に所有者不明となっている土地の有効活用を促進することを目的としています 。
本稿では、相続土地国庫帰属制度の概要、申請できる方、対象となる土地、手続きの流れ、費用、そして利用する際のメリット・デメリットについて分かりやすく解説いたします。
相続した土地の扱いに困っている方は、ぜひご一読ください。
・相続土地国庫帰属制度の概要
・申請の手続きや流れ
・制度のメリット、デメリット
誰が申請できる?どのような土地が対象となる?
申請できる方
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、原則として、相続または相続人に対する遺贈によって土地の所有権を取得した方に限られます 。
もし相続した土地が共有名義となっている場合は、相続によって共有持分を取得した共有者全員で共同して申請する必要があります 。
一方で、生前贈与によって土地を取得した場合や、ご自身で購入した土地は制度の対象外となります 。
また、法人名義での申請は原則として認められていません 。
対象となる土地
相続土地国庫帰属制度の対象となる土地には、いくつかの条件があります。
- 手放したい土地の上に建物が存在しないこと
- 抵当権や賃借権などの権利が設定されていない土地であること
- 道路や水路、墓地などの、他の人が利用することが予定されていない土地であること
- 土地の境界が明確であること
上記のほかにも細かい条件などが定められていますので、詳しくは法務省のサイトをご確認ください。
さらに、申請が却下されるわけではありませんが、承認されない可能性のある土地もあります。
例えば、傾斜の強い斜面がある土地やがけ地で、管理に過大な費用や労力がかかる場合 や、土地の管理や処分に影響のある工作物、車両、樹木などが存在する土地 、除去しなければ土地の通常の管理や処分ができない有体物が地下に埋まっている土地 、隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地 などが該当します。
申請の流れ:手続きを分かりやすく解説
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、以下の手順で手続きを進めます 。
相談は予約制で、対象となる土地の所在地を管轄する法務局(本局)で相談を受け付けています。
相談の際には、法務省ホームページにある「相続土地国庫帰属制度相談票」「チェックシート」を記入して持参します。
また、土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書、土地の現況が分かる写真などがある場合にはそれらも持参することがおすすめされています。
事前相談を終えたら、制度利用に必要な申請書などを作成します。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 申請書
- 申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- 申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- 申請に係る土地の形状を明らかにする写真
- 承認申請者の印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書(任意)
- 申請土地の境界等に関する資料(あれば)
- 申請土地にたどり着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
- その他相談時に提出を求められた資料
上記の書類を作成し終わったら、土地の所在地を管轄する法務局(本局)へ持参もしくは郵送(書留またはレターパックプラス)して提出します。
申請には土地一筆あたり14,000円の手数料を収入印紙で納付する必要があります。
申請書一式が法務局に到達し、受理されると審査が開始されます。
提出された書類の審査に加えて、場合によっては法務局の担当官が土地の現地調査を行います。
この際、土地の状況次第では申請者自身も現地調査への立ち合いが必要になることもあります。
審査の結果、要件を満たしていると認められれば、法務大臣による承認が得られます。
申請が承認されると、法務局より承認通知と負担金の納付通知が送付されてきます。
負担金は、国庫帰属が承認された土地の10年分の管理費用に相当する額で、通知書に記載されている金額を通知書到着の翌日から30日以内に納付する必要があります。
負担金の納付が完了すると、土地の所有権が国庫へ帰属します。
所有権移転の登記手続きは国が行うため、申請者が別途手続きを行う必要はありません。
費用について:審査手数料と負担金
相続土地国庫帰属制度の利用には費用が発生します。
主な費用として、審査手数料と負担金があります。
審査手数料(審査手数料)
申請時に、土地一筆あたり14,000円の審査手数料が必要です。
負担金(負担金)
申請が承認された場合にのみ発生する費用で、国が引き取った土地の管理・処分にかかる費用の一部を負担するものです。
負担金の額は、土地の種類や所在する地域によって異なりますが、原則として一筆あたり20万円です。
ただし、市街化区域や用途地域が指定されている宅地、農用地区域内の農地、森林などについては、面積に応じて負担金が算出される場合があります。
| 土地の種類 | 基本的な負担金 | 備考 |
|---|---|---|
| 宅地 | 20万円 | 市街化区域や用途地域内は面積に応じて変動 |
| 農用地(田・畑など) | 20万円 | 市街化区域、農用地区域などは面積に応じて変動 |
| 森林 | 面積に応じて算出 | |
| その他(雑種地、原野など) | 20万円 |
正確な負担金額については、法務省のウェブサイトで詳細な計算方法や自動計算シートが提供されていますのでご確認ください 。
相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリット
メリット
相続土地国庫帰属制度を利用する主なメリットは、以下の通りです。
- 不要な土地を手放せる: 特に売却や活用が難しい土地を国に引き取ってもらうことができます。
- 管理・維持の負担軽減: 固定資産税の支払いや土地の管理の手間から解放されます。
- 多様な土地が対象: 売却が難しい農地や山林なども対象となる可能性があります。
- 安心の管理: 国が新たな所有者となるため、その後の管理について安心感があります。
- 他の相続財産への影響なし: 相続放棄とは異なり、不要な土地のみを手放し、他の相続財産は維持できます。
デメリット
一方で、相続土地国庫帰属制度には以下のようなデメリットも存在します。
- 費用がかかる: 審査手数料と負担金の支払いが必要となり、土地の種類や状況によっては高額になる場合があります。
- 対象となる土地が限定的: 全ての相続土地が対象となるわけではなく、様々な要件を満たす必要があります。
- 手続きに時間がかかる: 申請から国庫帰属まで、半年から1年程度の期間を要することがあります。
- 共有名義の土地は全員の同意が必要: 相続した土地が共有名義の場合、共有者全員が同意し、共同で申請する必要があります。
相続した土地を手放す方法としては相続放棄という選択肢もありますが、相続放棄は全ての相続財産を放棄することになるため、慎重な判断が必要です。
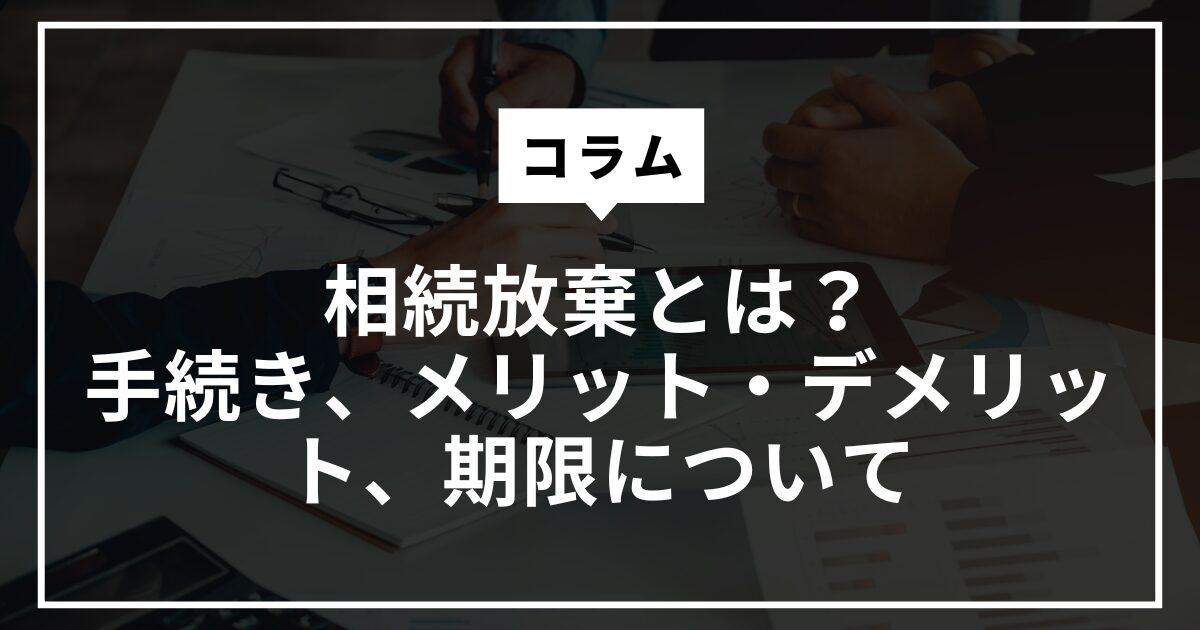
おわりに
相続土地国庫帰属制度は、不要な相続土地の処分を検討する上で、有力な選択肢の一つとなり得ます。
しかし、申請には様々な要件や手続き、費用が発生するため、ご自身の状況に合わせて慎重に判断する必要があります。
当事務所では、相続土地国庫帰属制度に関するご相談を承っております。
制度の利用が可能かどうか、どのような手続きが必要か、費用はどの程度かかるかなど、お客様の個別の状況に合わせて丁寧にアドバイスさせていただきます。
「相続した土地の扱いに困っている」といったお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談・お問い合わせください。
お問い合わせは以下のフォームよりお願いいたします。
最後までご覧いただきありがとうございました。
相談の予約・お問い合わせは以下のフォームより受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
