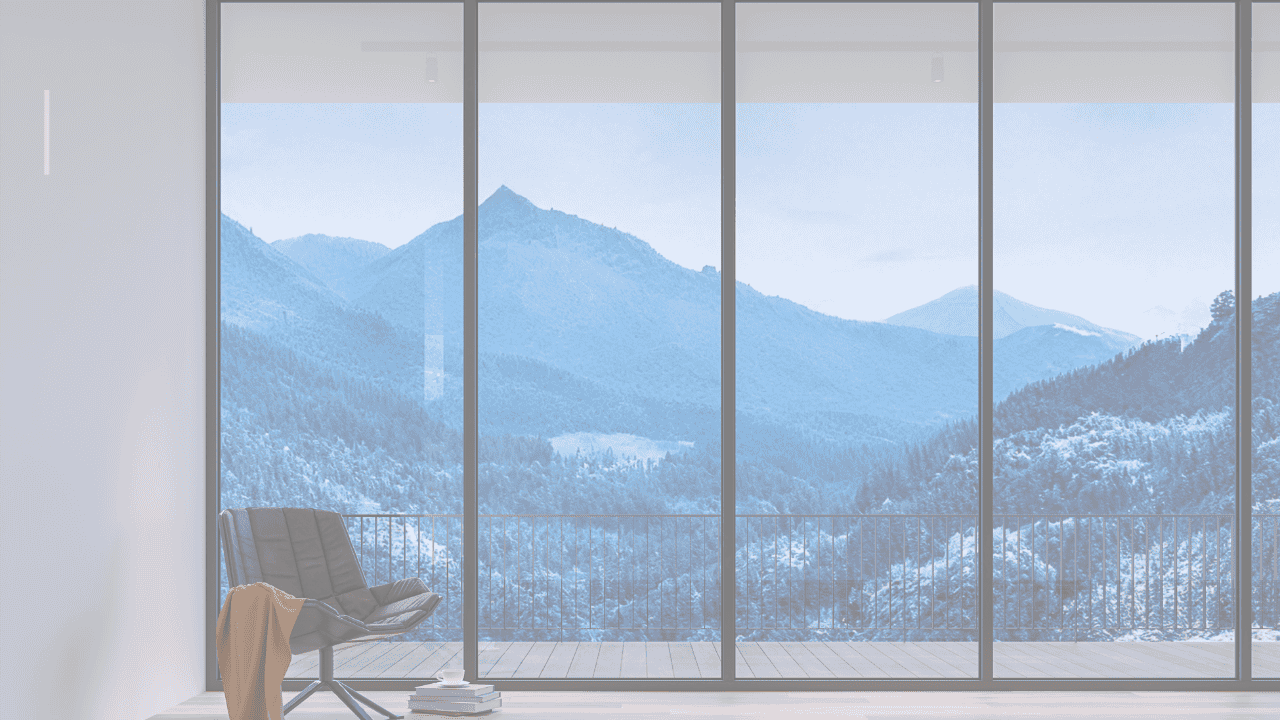みなさんこんにちは。須賀川市で相続を専門に取り扱っている司法書士の黒田匠です。
最近では「終活」や「エンディングノート」など、人生の最後を綺麗に締めくくるための活動を行う方が増えてきています。
今回はそういった活動の一つである、「遺言書」の種類や作成方法などについて解説していきたいと思います。
・遺言書の種類とそれぞれの作成方法
・おすすめの遺言書の種類
・遺言書を作るべきか
遺言書とは
遺言書とは、遺言を書き記した書面のことであり、自身の最後の意思表示ともいえます。
遺言は法律でその様式が定められており、正しい様式で記載がされないと内容が全て無効になる可能性があります。
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
民法960条
自分の財産や思いを間違いなく後の世代へ伝えられるよう、正しい遺言書の作り方を知っておきましょう
遺言の効力
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
民法964条
民法964条には、遺言によってできることが書かれています。条文では難しく書かれていますが、砕けた言い方をすると、
「自分の財産を誰に対して、どのように分けるかを遺言書で決められる」といったところです。
財産の全てを特定の一人に相続させたり、贈与したりすることもできますし、相続人全員に対して均等の割合で財産を相続させる、といった内容も成立します。
遺言の種類とそれぞれの作成方法
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の方式があり、それぞれ長所と短所があります。
自筆証書遺言
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
民法968条
自筆証書遺言とは、遺言の全文章、日付、氏名を自分で書き、さらに押印をしたものになります。
自筆証書遺言は作成の手軽さがメリットですが、その反面紛失のリスクやそもそも相続人が遺言書を発見してくれないなど、自分の死後に適切に意志を伝えることができないリスクがあります。
公正証書遺言
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
民法969条
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
条文が長く読みづらいですが、簡単に説明すると公正証書遺言とは、①公証人という人の前で遺言の内容を確認し、②公証人が遺言書を作成した後、③遺言を残す人と、それを証する証人2人が署名押印したもの、となります。
公正証書遺言は作成のためにいろいろな手間がかかりますが、法律のプロフェッショナルが作成に携わるため、間違いのない遺言が完成します。また、作成した遺言書の原本は公証役場という場所で保管されるため、紛失のリスクも最低限に抑えることができます。
秘密証書遺言
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
民法970条
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
こちらも条文が長いですが、秘密証書遺言とは、自筆証書遺言のように遺言書を作成した後、封をして押印し、その存在だけを公証人と証人2人に知らせる遺言書のことです。
秘密証書遺言は利用数が少なく、秘密証書遺言も公正証書遺言も公証人が関わるため、どちらかというと内容が無効になりにくい公正証書遺言を利用する方が多いです。
遺言書は作るべき?
ここまで3種類の遺言書を説明してきましたが、そもそも遺言書を作成するべきなのかという疑問が浮かんでくる方もいるかと思います。
私見をお話しすると、誰しもが遺言書を作成するべきだと考えています。
自分には大した財産が無いから不要だ、自分には子供も特にいないから大丈夫だ、という方がいらっしゃいますが、むしろそういった方こそ遺言書を作成した方がよいです。
財産が僅少でありながらも相続人間でトラブルになるケース、子供がいないまま亡くなって親や兄弟が相続人となったばかりに相続関係が複雑になるケースなどが近年多くなっています。
遺言書があることでスムーズに相続手続きが進むため、ぜひとも遺言書を作成することをおすすめします。
おすすめの遺言書の方式は?
ここまで3種類の遺言書の方式を説明しましたが、おすすめする遺言書の方式は「公正証書遺言」になります。
たしかに費用と手間はかかってしまうのですが、遺言の内容がほとんど無効にならないメリットが大変大きいです。
そもそも遺言を遺すというのは、ご自身の最後の気持ちを伝える面もありますが、亡くなった後の相続トラブルを未然に防ぐ効果もあります。
遺言が無効となってしまったばかりに、誰が遺産を相続するのかで揉めることはよくあり、結果として遺産分割の調停や裁判に至るケースも見受けられます。
そうなってしまえば余計に相続人で手間や費用が発生してしまいますので、間違いのない公正証書遺言で遺言書を作成しておくことをおすすめします。
こんな遺言書はアリなの?過去の事例と遺言の成立可否について
公正証書遺言をおすすめしましたが、自筆証書遺言では過去にこのような事例がありました。
日付に「昭和四拾壱年七月吉日」と書いた自筆証書遺言は有効?
自筆証書遺言では、日付を自書する必要があると述べましたが、果たしてこの「吉日」というのは日付として認められるのでしょうか?
これに対して裁判所は、「吉日」というのは、暦上の特定の日付を表示しているものではないとして、遺言書全体が無効となる判断を下しています。(最判昭和54年5月31日)
氏名にペンネームを記入した自筆証書遺言は有効?
同じく、自筆証書遺言では氏名を自書する必要がありますが、ペンネームが自書された遺言書は有効なのでしょうか?
大正時代に出された判例ですが、このケースでは、ペンネームによって遺言者本人である(同一性がある)と判断され、遺言書は有効なものと扱われました。(大判大4.7.3)
しかし、無効と判断される可能性もあるため、何かよほど特別な理由がない限りはご自身の本名を記入される方がよいでしょう。
おわりに
いかがだったでしょうか。3種類の遺言書の方式が少しはお分かりいただけたかと思います。
ご自身の状況に合わせて最もよいと思う方式で遺言書を作成されてみてはいかがでしょうか?
黒田司法書士事務所では遺言書作成の相談も対応しております。
遺言書を作成してみたいけどやっぱりどう作っていいかわからない、公正証書遺言を作りたいけど証人を頼める人がいないなど、お困りのことがあればぜひ当事務所へご相談ください。
お問い合わせは以下のボタンよりお願いいたします。
記事を最後までご覧くださりありがとうございました。
相談の予約・お問い合わせは以下のフォームより受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。